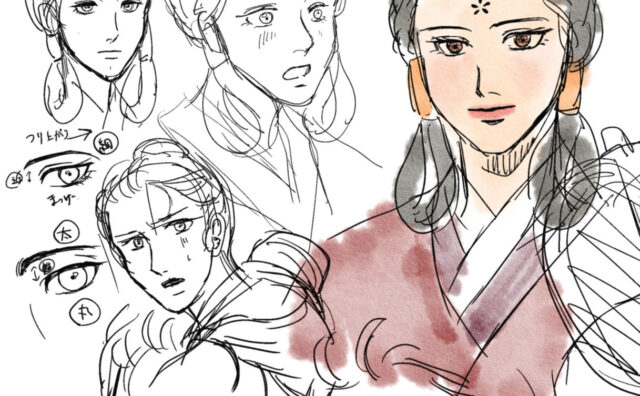奈良時代の結婚制度について調べたことをまとめるページです。
原稿の合間に随時更新中です。
奈良時代の夫婦の離婚と再婚、子供の姓の扱いについて記載しました。
この記事では、奈良時代の結婚制度についてまとめています。
現代社会の結婚およびそれにまつわる制度についての主張や思想はいっさいありません。
奈良時代の結婚は
- 通い婚(妻問い婚。つまどいこん)が一般的だったと言われているが、それぞれの家庭の事情による部分もある。
- 夫婦は別姓。子供は原則的に父方の姓を名乗る。
- 結婚可能年齢は男性15歳~、女性13歳~
です。
結婚可能年齢は養老令「戸令」による。
年齢は数え年である。
以下はまだまとめきれていない、ざっくりメモです。
そのうち詳細を記載しますね~
奈良時代に運用されていた律令制は中国から輸入した制度です。
そのため、家父長制の影響が反映された制度になっていました。
さまざまな里の庶民の戸籍を分析すると、有力な戸主(現代的にいうなら一族の家長)は、娘や妹を婚姻先の妻・妾として戸籍移動させない傾向があるようです。
結婚して子供を産んだあとでさえ、実家の戸籍に残り続けた「娘」「妹」が存在しました。
奈良時代の結婚は通い婚が一般的だったのか
テストの回答としては【妻問い婚が一般的でした】。
これで問題ありません。
ただ、当時の実際の制度の運用としては、それぞれの家庭環境による影響も相当数あったようです。
つまり、通い婚じゃなくて同居している夫婦もいました。
高貴な事例としては長屋王。
長屋王の正妻は吉備内親王(きび ないしんのう)です。
吉備内親王は、長屋王邸宅に住んでいた――つまり、夫 長屋王と同居していた可能性が高いようです。
ただし! 長屋王はトップクラスの貴族(というか王族)。
邸宅の敷地面積はとても広いです。この邸宅で日用品の自給自足ができるほどの生産施設があるほどでした。
ですので、「同居」といっても夫婦は別の棟に住んでいたと思われます。
夫であり、主人、家長、いまでいうと世帯主の長屋王と、妻 吉備内親王は、同じ敷地内の別の家に住んでいると言った方が現代人にはわかりやすいかも。
いっぽうで、長屋王の妾のひとりだった藤原長娥子(ふじわら の ながこ)は、長屋王とは違う邸宅に住んでいたと推測されています。
夫人たちの別居と同居の推測は、長屋王邸宅跡から出土した木簡の内容から考えられています。
正妻と妾。妻の位について
奈良時代は一夫多妻制ですが、正妻はただひとりです。
なお、この正妻は、奈良時代では【嫡妻(ちゃくさい)】といいました。
嫡妻とは、戸籍に記載される正式な妻ということ。
繰り返しになりますが、たったひとりです。
時代のニュアンスはずれるものの、正室といったほうがわかりやすい方もいらっしゃるかもしれませんね。
妾は、嫡妻(正妻)以外の妻のことです。
奈良時代では
- 男性の妻は複数いる
- その中のひとりが嫡妻(戸籍に記載される正式な妻)だった
ということです。
離婚と再婚は可能だったのか?
はい、可能でした!
基本的に妻問い婚は通い婚ですから、男性が女性のもとに通います。
そのため、男性が来なくなれば離婚成立です。
これを「夜離れ(よがれ)」といいました。
奈良時代の夫婦が離婚すると子供はどうなる?
奈良時代の夫婦が離婚すると、子供の養育は母親(妻)がおこないました。
なお、子供が名乗る姓は父方のものです。
この子供を連れた状態で、女性は再婚することも可能でした。
古代史と聞くと女性の自由が制限されていそうなイメージがわいてしまいますが、奈良時代の女性はわりと自由だったのかも……!?
離婚ではなくて死別ですが、子供の姓に関する例のひとつとして……
またも長屋王一家の例になりますが、長屋王と妾 藤原長娥子の間に生まれた子供たちはみんな「王」を名乗っています。
つまり、藤原の姓は名乗っていないのです。
子供たちのうち一人だけ、のちに、とある手柄(!?)と立てたことで藤原姓を名乗ることを許されています。
参考文献
ひとまず覚えているものだけ挙げておきます。