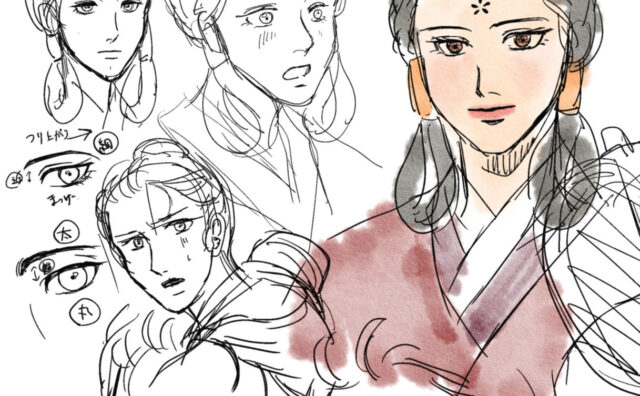2024年12月21日(土)、平城宮いざない館でNPO法人 奈良好き人のつどい さん主催の有料講座が開かれました。そのときに「平城京 すまいと暮らし」の話を学びました。
教えてくださったのは、公益財団法人 元興寺文化財研究所の田邊征夫所長です。
ここで学んだことをシェアします。
仏教による鎮護国家思想だった奈良時代ですが、普通に肉食してます。
情報ソースはなんと、木簡と出土品。
さらに平城京(奈良)は海なし県であるにもかかわらず、肉のほかに魚も食べています。グルメ!?
肉を食べていると思うと、平安時代よりも栄養のバリエーションとしては豊富なのでは……!?
奈良時代の食材。肉類は
- 鹿(シカ)
- 雉(キジ)
- 猪(イノシシ)
- 兎(ウサギ)
- 鶉(ウズラ)
- 鴨(カモ)
- 鳩(ハト)
- 馬(ウマ)
- 牛(ウシ)
- 鯨(クジラ)
- 海豚(イルカ)
「鹿は神の使いじゃないの!?」って気がしますが、鹿も食べられていたようですね。
奈良に鹿がやってきたのは西暦768年のことだと言われているので、ひょっとしたら鹿が食べられていたのはそれ以前のことなのでしょうか。訊いておけばよかったです!
奈良時代は西暦710年~784年(または794年)です。
豚(ブタ) ≒ 猪(イノシシ)だと思うと、鳥肉と豚肉と牛肉と……現代に匹敵するバリエーション……?
むしろ、クジラやイルカが入っている分、現代よりも種類は豊富といえるのかもしれません……(それぞれどれくらいの頻度で食べられていたのかはわかりませんが……
奈良時代の食材。水産物は
以下の漢字表記は当時の表記(万葉仮名含む)になっています。
海魚
- アジ(鰺)
- カツオ(堅魚)
- サバ(鯖)
- カマス(加麻須)
- スズキ(須々支)
- タイ(鯛・多比)
- クロダイ(知奴。チヌ)
- サケ(鮭)
- マス(鱒)
- イワシ(鰯・伊委之・伊和志)
- サメ(鮫・佐米)
- イカ(烏賊・伊加)
- タコ(蛸)
- カレイ(鰈)
- ヒラメ(平目)
- ボラ(鯔)
など……
甲殻類
- カニ(蟹)
- エビ(海老)
川魚
- アユ(鮎・年魚)
- フナ(鮒・布奈)
- ウナギ(鰻)
貝類
- アワビ(鮑・鰒)
- カキ(河鬼)
- ハマグリ(蛤)
- イガイ(貽貝)
など……
その他
- ウニ(蕀甲蠃)
- クラゲ(水母)
- ナマコ(生海鼠)
- ホヤ(冨也)
- メ(海藻)
- ワカメ(和海藻)
- アラメ(荒海藻)
- イギス(伊支須)
- ミル(海松)
- ツノマタ(鹿角菜)
- カジメ(未滑海藻)
- ムラサキノリ(紫菜)
など……
河豚(フグ)は食べてなかったの?
もんのすごいバリエーションの水産物を書きましたが、ここにフグが含まれていないことに気づかれましたか?
フグという語句は平安時代のものらしく、奈良時代にはどのような名称で呼ばれていたのかまだわかっていないそうです。
でも、フグが食べられていたことは確実だろう、とのことでした。
というのも、縄文時代の出土品にそれを裏づける証拠があるからです。
つまり、縄文時代にはすでにフグが食べられていました。
奈良時代の木簡にはなぜかその名称が出てきませんが……
これから発掘調査が進むと、フグの名称がはっきりわかる木簡などが出土するかもしれませんね!
生魚は食べていたのか?
生魚は食べていました。
ええええええもう現代と変わりませんね!
これは私が学んだことですが、それを裏づける証明として天然痘パンデミック(天平の疫病大流行)が起こったときのことがあげられます。
天平9年(737年)6月26日付の公文書(太政官符/だいじょうかんぷ、だじょうかんぷ)の記載に興味深い箇所があります。
重湯、粥、煎飯、粟等の汁は温冷問わず好みで与える。鮮魚・冷肉・果物・生野菜はいけない。特に生水・氷はかたく慎むように。下痢を起こしたら、煮た韮や葱を多く食べさせると良い。血便や乳状便が出たら、糯粉と米粉を混ぜて煮、一日に数度飲ませる。又、糯や粳の糒を湯で溶いたものを用いる。
(中略)
回復後も20日間は鮮魚・冷肉・果物・生野菜を摂取してはいけないし、生水・水浴・房事のたぐいや、風雨の中を歩いたりすることも慎むように。もしこの注意を守らないと必ず霍乱(かくらん)になって下痢を再発する。これを勢発・労発というのだが、そうなったら、愈跗(ゆふ)・扁鵲(へんじゃく)のような中国古代の名医を連れてきても手遅れである。20日過ぎれば魚も肉もいい。ただよく炙ってから食べる。乾鮑(ほしあわび)・堅魚(なまりぶし)・乾肉の類もいいだろう。しかし、鯖(さば)や鯵(あじ)はたとえ干物でも止めておくように。年魚(あゆ)もいけない。蘇(乳製品)・蜜・豉(豆腐)などはいい。
この太政官符は、疫病にかかったときの治療法や注意をまとめたものです。
こんな大事なものに「鮮魚(中略)はいけない」とわざわざ書かれるのは、鮮魚(生魚)を食べる機会があったことにほかなりません。
奈良時代の食材。野菜は
- ウリ(瓜)
- キュウリ(青瓜か? 種子出土)
- マクワウリ(黄瓜か? 種子出土)
- ダイコン(大根・蘿葡など)
- カブ(菁菜)
- ネギ(葱)
- ニンジン(人参)
- カラナス(韓茄子)
- ヤマイモ(暑預。じょうよ?)
- サトイモ(家芋)
- フキ(蕗)
- ミョウガ(茗荷)
- ショウガ(生薑)
- ジュンサイ(蓴菜)
- トウガン(毛瓜)
- ニラ(韮)
- ノビル(蒜)
- セリ(芹)
- ワラビ(蕨)
- タラ(太羅)
- チシャ(智佐)
- アイ(阿布比)
- ハス(蓮)
- レンコン(蓮根)
- マツタケ(松茸)
- アザミ(薊・阿射美)
- ニガナ(荼)
- ナギ(水葱・奈木)
- クズ(葛)
など……
奈良時代の食材。果物は
- カキ(意比)
- ナシ(梨)
- ミカン(甘子)
- ウメ(梅)
- モモ(桃)
- クリ(栗)
- ビワ(枇杷)
- タチバナ(橘)
- クルミ(胡桃)
- ヤマモモ(山桃)
- ナツメ(棗)
- タケノコ(竹子)
- マツ(松)
- ヒシ(菱)
- トチ(橡)
- シイ(椎)
など……
奈良時代のお菓子は果物。現代でいうお菓子=唐菓子
現代でお菓子というとき、果物はまず連想しませんよね。
奈良時代ではお菓子というと、果物を意味しました。
現代でイメージする菓子は、奈良時代では「唐菓子(からかし)」といいます。
梓澤要先生の奈良時代を扱った小説では、「麦縄(むぎなわ)」というお菓子(唐菓子)を食べるシーンがたびたび登場します。
「麦縄」は、小麦粉を練って油で揚げたものです。
そこに甘葛(あまづら)をかけたりして食べます。
きなこをまぶすシーンもありました。
ただし、唐菓子も甘葛も、砂糖不使用・蜂蜜不使用です!!
奈良時代の砂糖や蜂蜜は超超超~~~~~貴重品!!
薬扱いです。調味料として気軽に使えるものではありません。
奈良時代の甘味料事情
奈良時代、砂糖やはちみつはとっても貴重品です。
調味料として気軽に使えるものではなく、薬として扱われていました。
どのくらい貴重かというと、たとえば砂糖は正倉院に納められるくらいです。うわあ……
「正倉院献納目録」の「種々薬帖」に「蔗糖二斤一二両三分併椀」との記載があります。
鑑真和上によって砂糖はもたらされたという説もあるよ。
※鑑真和上が日本にやってきたのは西暦753年(天平勝宝5年)だよ。
長屋王は氷室を持っていて、夏にはかき氷を食べていたのでは? なんて話もありますが……
そのときのシロップは「甘葛(あまづら。甘葛煎/あまづらせん ともいう)」だったのでは、といわれています。
甘葛はぶどう科のツル性植物からさまざまな手順を踏んで作られます。
どの植物で作るのかは、まだはっきりとはわかっていないようですね。
「甘葛」の再現を目指した「甘葛シロップ」は、平城宮いざない館の売店で販売されています。1500円くらい。
奈良時代の調味料、香辛料は
- 塩
- こなみそ(末醤/まっしょう。味噌の原形?)
- 醤(ひしお)
- 酢
- ごま油
- 鰯の煮凝り
- 煮凝り
- 飴
- 蜜(ただし蜂蜜は除く)
- 辛子
- 生薑(しょうきょう。しょうが)
- 山椒
- 搗き韮蓼(つきにらたで?)
- 薄荷
砂糖を除けば、料理の「さしすせそ」はそろっているともいえるんですね。
塩、酢、しょうゆ(≒ひしお)、みそ(こなみそ)……
奈良時代の酒類は
- 清酒
- 白酒
- 難酒
- 古滓
奈良時代のお酒の基本はにごり酒です。済んだお酒は高級品。
奈良時代の清酒は現代の清酒とは違うものです。
にごり酒の上澄みだけのことを「清酒」としていました。
居酒屋(酒肆/しゅし)も存在していたことがわかっています。
ただし、平城京内のどこに存在していたのかは不明です。
奈良時代の乳製品は
- 牛乳
- 蘇(そ。チーズのようなもの)
「蘇」は牛乳をひたすら煮詰めることで家庭でも再現可能です。
独身一人暮らしだったとき、レオパレ〇の電磁調理器で8時間にわたって牛乳を煮詰めつづけ、蘇を再現したことがあります。笑
甘味料を入れていなくても甘くて美味しいですよ。
参考文献
- 『平城京 すまいと暮らし』公益財団法人 元興寺文化財研究所 田邊征夫所長 2024年12月21日(土)平城宮いざない館
- 『奈良文化財研究所 編 奈良の都の暮らしぶり~平城京の生活誌~』